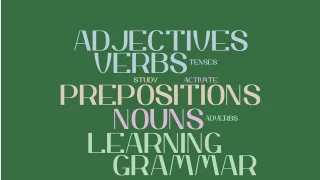みなさんこんにちは。
今日は第二言語研究と、それに基づく教授法について書いていきたいと思います。
おそらく聞いたことのあるよというような、文法訳読法やコミュニカティブアプローチなどについてのそれぞれの特徴を簡単に見ていきましょう。
まずは伝説の文法訳読法(Grammar translation Method)
おそらく日本人で英語教育を受けた方なら全員が知っているであろう教授法です。
その理由は、日本で一番多く採用されている教授法だからです。
一つのテキストを前から順番に母語に訳していき、必要に応じて文法項目をピックアップしていき解説していく。
おそらく多くの人が自分の学生時代を思い浮かべたのではないでしょうか?笑
これが文法訳読法です。
この文法訳読法は、1840年代〜1940年代あたりに「外国語学習の目的は、外国語で書かれた文学を読み、精神的、知的に成長することだ」というような考えのもとに考案されたものです。
目的の部分からもわかるように、バリバリ読解に重点を置いた教授法なんですね。
言い換えれば、文法訳読法は近年頻繁に批判されていますが、読解力に関しての教授法としては未だに優秀な教授法なんです。
近年ではコミュニケーション重視の教授法が模索されているために批判されやすいということですね。
そのあと、1930年代〜1960年代にかけて、行動主義に基づいた第二言語研究が盛んになります。
この行動主義の考え方のもとでは、「行動は何度も繰り返されることでやがて習慣になる」と考えられており、「言語の習得もそれと同じだ」という考え方でした。
つまり、「第二言語も何度も繰り返すことで、それはやがて習慣となる、つまり習得できる」という考えです。
このような行動主義の考え方に加え、対照分析仮説という考えをプラスして生まれたのがオーディオリンガルメソッド(Audio-Lingual Method)、別名オーラルアプローチ。(厳密に言えばオーディオリンガルメソッドはオーラルアプローチの進化版です)
軍隊の言語指導にも用いられていたため、別名アーミーメソッドとも呼ばれています。(かっこいい・・・)
ちなみに、対照分析仮説とは、「学習者の母語と、目標言語を比較することで、学習者にとって習得が難しいものは何かが予想でき、それを見つけることで教授をより効率的にできる」という考え方です。
なので、オーディオリンガルメソッドは簡単に表すと、「母語と習得しようとする言語との違いがある部分を重点的に繰り返し練習し、習慣化させることで第二言語は習得可能なんだ」という理論のもと生まれた教授法です。
したがって、この教授法に基づいた指導には、パターンプラクティス(例えばI have a pen. という例文を見たあと、主語を代えてYou have a pen.というような文を作る練習)やドリル学習(小学校の時に漢字ドリルや計算ドリルっというのをやりましたよね?同じような問題を解きまくるやつです)というようなものが中心となってきます。
個人的にはこの行動主義に基づく言語習得論、かなり賛成です。(言語の違いの部分だけに着目するのはやはりまずいと思いますが)
生得性の部分でも少しお話ししましたが、僕はUG否定派のため、この繰り返すことで習慣化されるという理論がものすごくしっくりくるんですね。(UGや生得性について知りたい人はこちら)
っということはおいといて、話を進めましょう。
結果的にいうと、このオーディオリンガルメソッド、ある程度の成功を収めるんですが、致命的な欠点がありました。
それは・・・
楽しくない!!
「え?それだけ?」、ってなりましたか?
これ致命的な欠点です。
おそらく言語を習得する上で一番の楽しみというのは他の人とコミュイケーションを取ることなんです。
どうして僕たち人間が言葉を使うのか。
それは他の人とコミュニケーションをとるためですよね?
コミュニケーションをとる必要がなければ言葉なんていりません。
自分を表現する必要がなくなるんですから。
第二言語だって同じです。
習得したからには使わないと楽しくない。
しかしこのオーディオリンガルメソッドではパターン化を図っていくため、コミュニケーション能力をつけることができなかったんですね。
そこで生まれてきたのが近年大流行中のコミュニカティブアプローチ。
「言語習得の最大の目的はコミュニケーションをとることにあるんだから、コミュニケーション能力を育てられるような教え方をしなさい!!!」っということですね。
「今までのような文法中心で、細かい間違いばかりを気にしていると英語は話せないので、意味を伝えることに集中して、間違いを恐れずどんどん話すようにしましょう」ってな考え方です。
少し話がそれますが、ここで二つの言葉を紹介しておきます。
上で述べたような文法に焦点を当てた教授法をフォーカスオンフォームズ(Forcus on Forms)、今述べたような意味に焦点を当てた教授法をフォーカスオンミーニング(Focus on Meaning)と呼びます。
形式に焦点を当てているからフォームにフォーカス、意味に焦点を当てているからミーニングにフォーカスって感じです。
っということで本題に
しかし!!
ここでさらに問題が発生します。
今度は意味伝達ばかりに焦点をあてていると、文法項目がだんだんめちゃくちゃになってくるんですね。
例えば、”Yesterday, I are going to the town.”という言葉を聞いた場合にでも、「昨日タウンに行ったんやなぁ」って理解できますよね。
後ろの青い部分が文法的に正しくなくても。
っということで、1990年代あたりから「意味伝達ばっかに焦点を当てるのは良くないんちゃうか?」って考えられるようになってきました。
なら、「意味伝達を中心とした教え方に、形式にも気をつけるような教え方にしたらいいやん!」っていうのが出た結論です。
つまり、「フォーカスオンフォームズとフォーカスオンミーニングを足したらいいやん」って感覚です。(厳密にいうと違うんですがイメージとしてはこの考え方でいいと思います)
その結果誕生したのがフォーカスオンフォーム(Focus on Form)。
え?
間違ってませんよ。
誕生したのはフォーカスオンフォーム。
形式を中心にした教え方はフォーカスオンフォームズです。
間違いやすいので気を付けましょう・・・笑
そして、一番のポイントは、フォーカスオンフォームでは、「コミュニケーションの流れのもとで文法的な知識も学習していきましょう」という点です。
今までは、例えば関係代名詞の使い方を学習したあとに、「はい、では実際に使ってみましょう」というような感じでした。
しかし、このフォーカスオンフォームでは、会話の流れから、例えば生徒が”*I go to the library yesterday.”と発言した場合、教師は生徒が自ら間違いに気付くように”You went to the library?”などのリキャストと呼ばれるフィードバックなどを用いて、会話の流れを遮らずに間違いを訂正するというのがポイントになります。(リキャストとは、教師が生徒の言いたいことの意味を変えずに、間違った部分を訂正した言い直しのことです)
今上で述べたように「自分で気づかせる」という点も一つのポイントで、フォーカスオンフォームには、気づき仮説という理論も深く関わっています。
今までの文法訳読法などでは教師が「この文法はこうだからこうなるんだよ」というように明示的に説明することが一般的だったんですが、このフォーカスオンフォームには気づき仮説の考え方が取り入れられているため、「生徒が自分自身で自分の誤りに気づくような指導をしましょう」というような考え方なんですね。
つまり、文法知識が全くない生徒に対しては少し難しいのではとも考えられます・・・
間違いに気づくことができないからです。
ではフォーカスオンフォームにはどのようなものがあるのか・・・
と説明したいのですがかなり長くなったのでその説明は次回!
今回は教授法の変遷を中心に書いたので、このような流れがあったんだな、という感じで頭に入れておいてください。
ではでは。
P.S.
日本で文法訳読法が流行っている理由はいろいろあると思いますが、個人的な意見としては大きく分けて2つあると思います。(ものすごく一般的な答えですが・・・笑)
一つは、一クラスの大きさですね。
文法訳読の授業は先生主導で行いやすいため、大人数の生徒相手に行うのに適しています。
一方コミュニケーション中心の授業の場合そうはいきません。
文章読解と異なり、答えがいくつもあるため全員に共通する答えを示せないからですね。
そしてもう一つは教員のレベル。
文法訳読を受けてきた教師はやはり読解に強く、コミュニケーション能力に弱い教員になってしまいます。
現在でもコミュニケーション能力に自信のある教員がどれだけいるでしょうか。
自信のないことを教えることはできません。
っということで、今の日本の英語教育は負のスパイラルに陥っているような気がします。(個人的意見です)